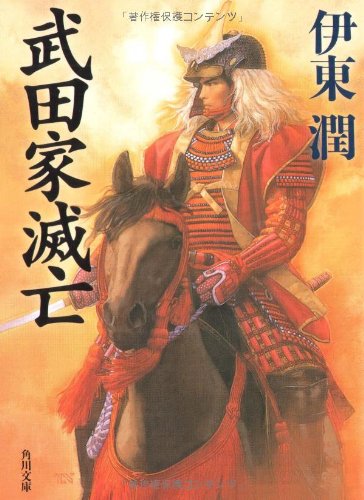
あらすじ
幼少時代から桂姫(桂林院)は、腹違いの兄で歳の近い三郎(景虎)を憧憬していた。その三郎が越後に行った後の天正五年(1577)、自らも甲斐の武田家に輿入れすることになる。夫婦となった勝頼と桂は、お互いを理解しようとつとめた。勝頼の複雑な生い立ちを聞いた桂は勝頼に同情し、母のような愛情を抱く。
しかし勝頼の周囲には、様々な人々がおり、前途の多難が予想された。それでも健気に武田家に溶け込もうとする桂だったが、北条家から随行してきた従者たちは、北条家と連絡を取ろうとして発覚する。桂の意思とは逆に、北条家から来た人々は次第に孤立していく。
一方、武田家の将来を憂いている春日虎綱(高坂弾正)は、宿老最後の生き残りとして自らを信奉する旗本の子弟らに、信玄の教えを伝えようとしていた。その中に小宮山内膳友晴と辻弥兵衛という二人の若者がいた。彼らは将来を嘱望される武田家の若手旗本であった。自らの死期を覚った虎綱は彼らに後事を託そうとする。
その頃、伊奈谷の一地侍宮下帯刀玄元は、寄親の片切監物昌為とともに高天神城に入ることを命じられる。徳川家と接する遠江の最前線の城である高天神城に入ることは、生還が期し難いことを意味した。
一方、武田家の本拠府中では、勝頼の懐刀である長坂釣閑光堅と釣閑の手足となって働く奉行の跡部大炊助が頭を抱えていた。彼らは武田家領土内の金山が枯渇しつつあること、さらに試掘していたいくつかの鉱脈も見込みがないことを知り、武田家が瓦解の危機に瀕していることを知る。金山は土地の貧しい武田家にとって軍資金の源泉であった。しかし、大炊助から伊豆土肥金山の可能性を聞いた釣閑は、北条家領土である伊豆への野心を抱く。
その頃、上方では、本願寺と泥沼の消耗戦を強いられている信長が、いよいよ謙信から上洛を告げられ苦境に陥っていた。そのため、信長は武田家との同盟を望んできた。
かくして、人々の様々な思惑を巻き込みつつ、武田家は崩壊へとひた走ってゆく。
書籍データ
価格: 940円税込
単行本: 645ページ
出版社: 角川書店
ISBN-10: 4043943210
ISBN-13: 978-4043943210
発売日: 2009/12/25
書評
山梨新報 4月6日朝刊書評欄(単行本版)
“健気に散った桂姫” 伊東潤氏の小説「武田家滅亡」
「桂姫」、それは歴史小説「武田家滅亡」の主役である勝頼夫人・北条氏への、作者伊東潤氏のネーミングである。信玄の側室で勝代の母諏訪御料人に新田次郎が小説「武田信玄」の中で湖衣姫と名づけ、井上靖の小説「風林火山」では由布姫と呼ばれていると同じように(作者注 : 「桂姫」とは、戒名桂林院殿から取られています)。
小説は、天正五(1577)年1月、桂姫が、上杉謙信の養子となって越後へいった北条三郎(後の上杉景虎)への想いを断ち切って、甲斐の武田勝頼に輿入れするため、相模小田原を発った日から始まる。それは武田・北条同盟のあかしであった。
その2年前の「長篠の合戦」の大敗以来、暗い戦雲が覆う甲斐国で、勝頼とともに必死に運命を切り開こうと、姫は健気に生きる。だが、天正十年(1582)2月、織田・徳川氏ばかりか、姫の実家・北条氏まで轡(くつわ)を揃えて甲斐国に攻め込むに及んで、武田氏の滅亡は必至となった。
その時、姫は、武田八幡に「敬って申す祈願の事」で始まる長文の願文を捧げた。
しかし、運命は好転せず、新府城を落ちた勝頼と桂姫は天目山麓の田野の里で滅亡する。
よく知られた滅亡史だが、桂姫の存在によって哀切な読み物となり、文芸評論家縄田一男氏に「これほどの作家が今までどこに隠れていたのか」と言わせている。







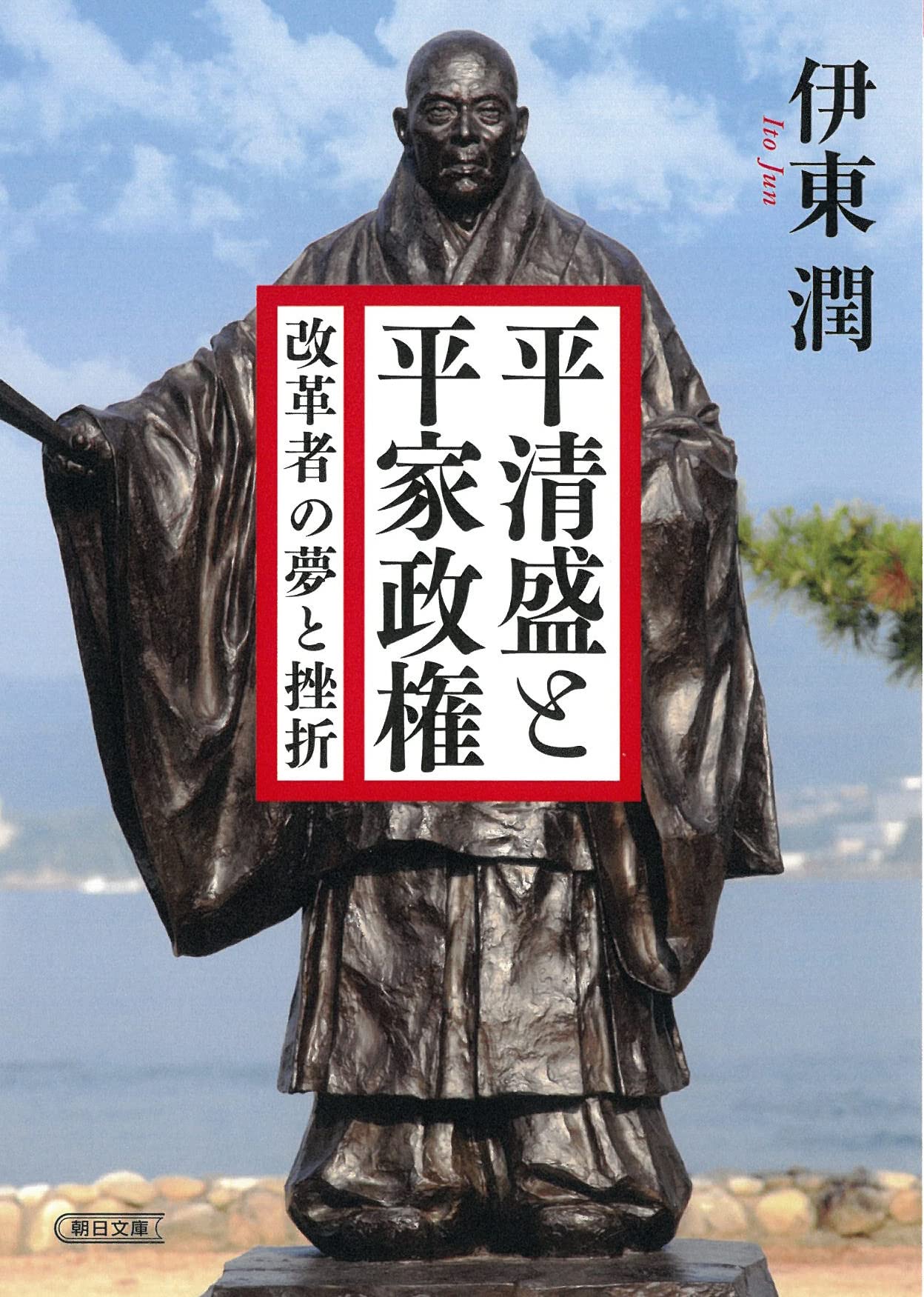









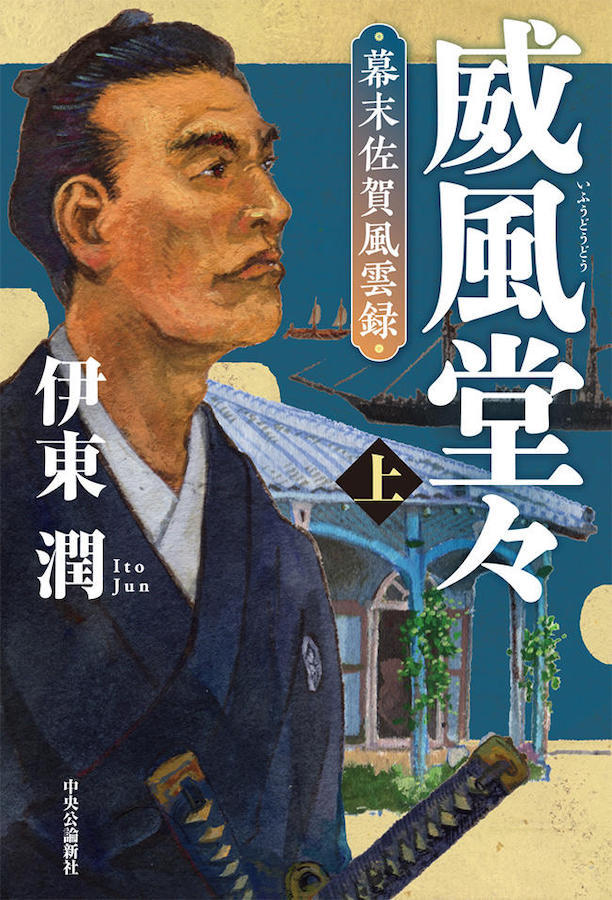




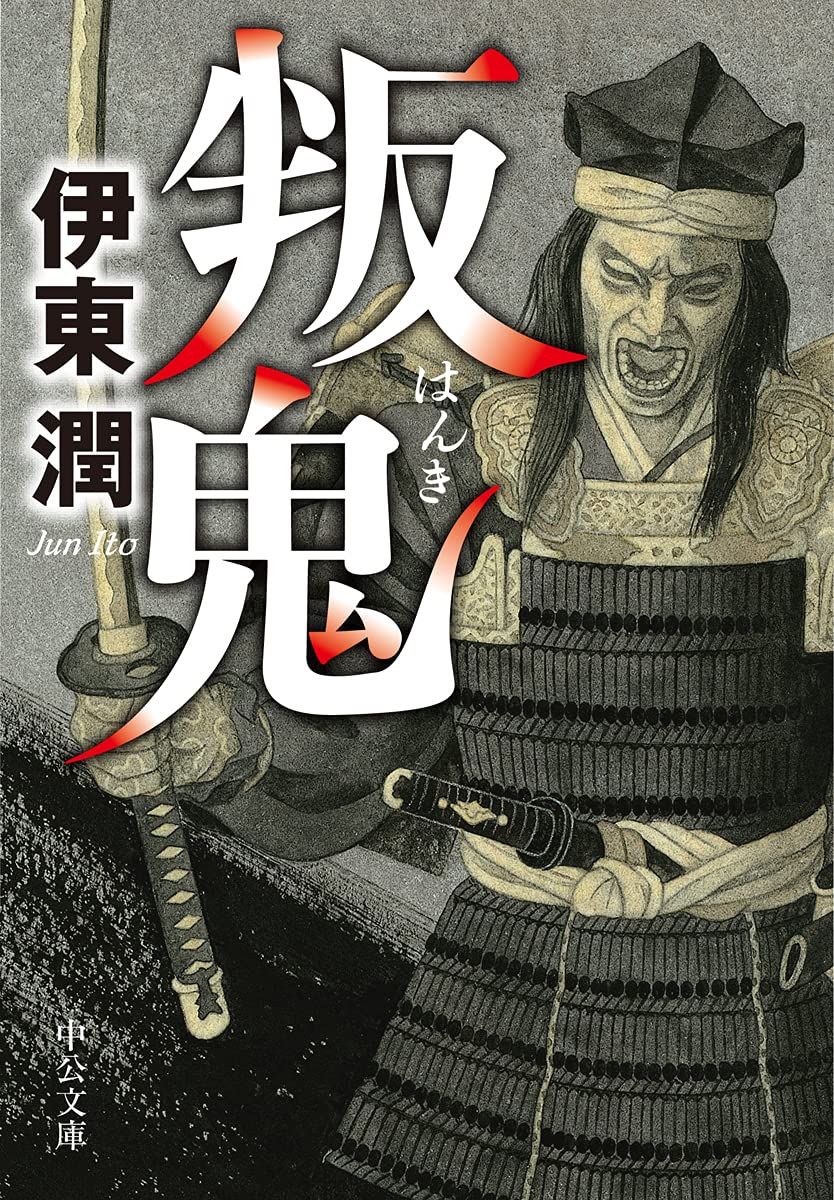
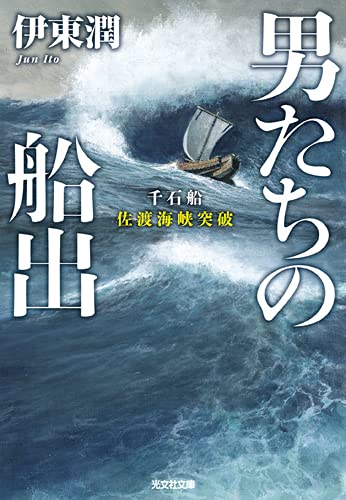













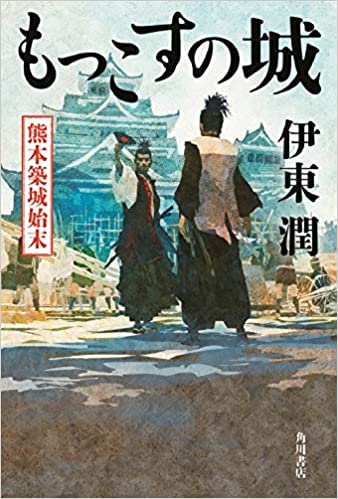





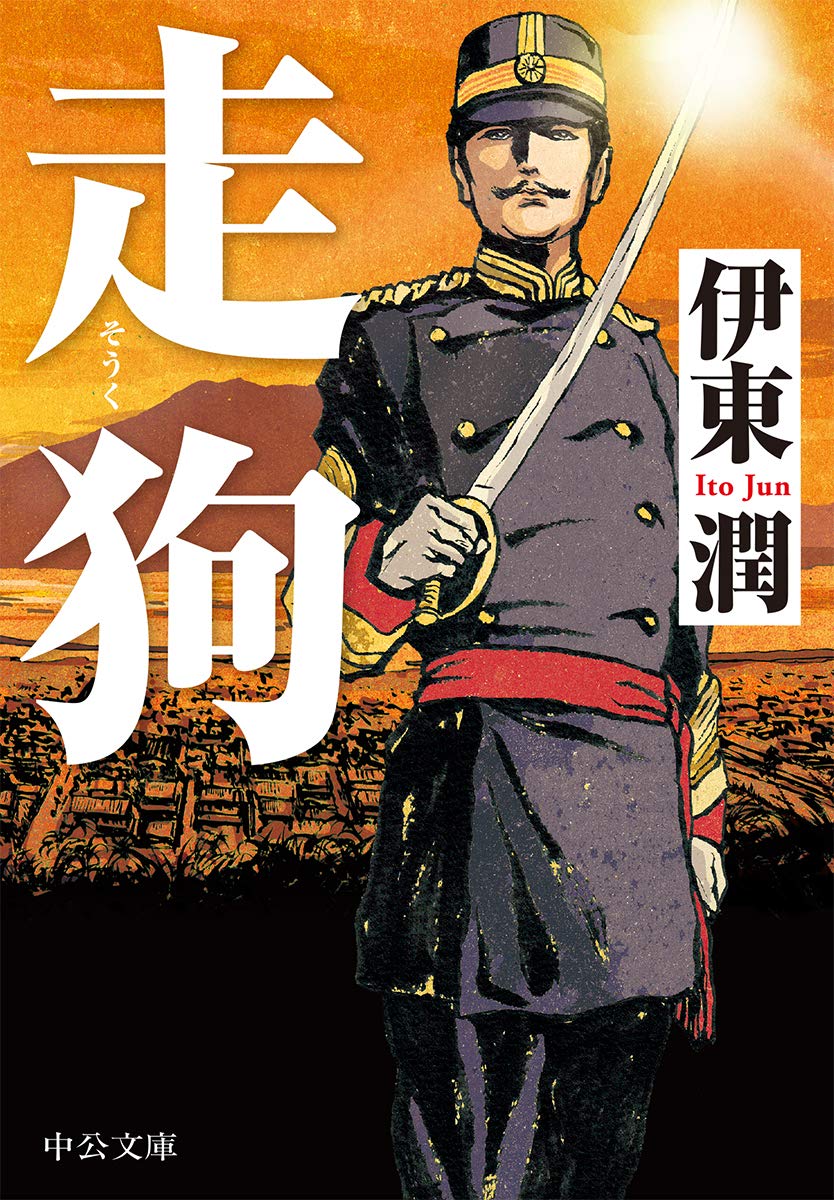



作者より
角川の編集者の方から全面的バックアップを受けて、まさに渾身の力を振り絞って書いた作品でした。いま思うと、よくぞあれだけ集中して書けたものだと思います。何せ、夜の睡眠を二回に分け、トータル4時間ほどの睡眠時間で半年ほど過ごしたのですから。
さて、この作品で、私の作風である「主役不在の群集劇」、「人ではなく事件中心」、「プロットは複雑に」、「布石と伏線を打ちまくる」という特徴が完成しました。感想をいただいた中に、「幾つもの伏線が怒涛のように暴れ狂うエンディングには、うならされました」というのがありましたが、まさに言い得て妙です(涙)。もはやここまでくると、従来型の「キャラ中心」、「語り口中心」、「にじみ出る情感中心」の時代/歴史小説の殻を打ち破り、新たなエンターテインメントの地平に歴史小説を立たせてしまった感があります。
前半は『刑事コロンボ』、後半は『24』の世界のパスティッシュ(モチーフ合成)と化し、そこにシェークスピアの『オセロ』が絡むのですから、まさに、ごった煮状態です(笑)。
かつて、ある個人の書評サイトで、『戦国関東血風録』について、「世界最高の材料を集めてフルコース料理を作るはずが、調理方法が分からず、ごった煮の鍋物になった」と評されましたが、まさにこの作品で、仇を取ったようなカタルシスを感じました。
題名は、当初、『獅子たちの落日 武田家滅亡異聞』だったのですが、スケールがでかいことから、ストレートで堂々とした題名に変えるべきという版元の意向に同意しました。『武田家滅亡』という題名には、初め違和感もあったのですが、今は慣れました。