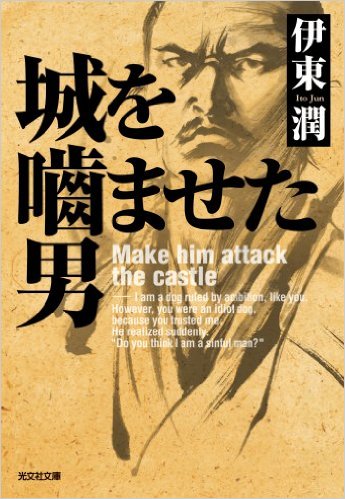
第146回直木賞候補作品
あらすじ
『見えすぎた物見』
南の渡良瀬川の辺り夥しい旗が見える。北条勢が来襲したのだ。
物見から知らせを聞いた佐野家筆頭家老の天徳寺宝衍(ほうえん)は、防戦の支度をするでもなく、佐野家の若き当主宗綱を引っ張り、唐沢山城を駆け下っていった。そして二人は、来襲した北条氏政に、ただひたすら頭を下げた。巨大勢力に対しては、意地も誇りも捨て、ただ頭を下げることが、この時代、中小国人が家を守る唯一の方法だったからである。
先を見通し、常に優勢な方につき、その命脈を保ってきた佐野氏。
宝衍は先祖の遺訓を守り、敵が来る度に、ひたすら頭を下げ続けた。
その結果、常に勝者の側に付くことのできた佐野家の将来は盤石に思えた。しかし、その先には、予想もつかない事態が待っていた。
『鯨のくる城』
天正十八年(1590)、小田原合戦が勃発し、秀吉の大軍が東国に迫っていた。平和だった伊豆の地も、戦場となるのは必至であった。
伊豆奥郡代・下田城代の清水康英は、伊豆の国人や海賊衆に対し、皆で団結し、下田城に籠ることを唱えるが、西伊豆海賊衆はその策に反対し、双方は決裂してしまう。
西伊豆衆は勝手におのおのの城に籠り、防戦に努めることとなり、一方、康英の唱える下田城籠城に賛同したのは、わずかな国人にすぎなかった。その兵力は六百――。
ところが秀吉水軍は強大で、次々と西伊豆諸城は降伏開城していった。
西伊豆を制圧した豊臣水軍は、続いて下田城に迫った。
下田籠城衆は、城を出て果敢に戦いを挑むが、矢玉も尽き、いよいよ降伏開城以外に手はなくなる。そんな時、康英に従い、共に下田城に籠っていた高橋丹波守という男が、鯨を獲りに行くと言い出した。
『城を噛ませた男』
天正十七年(1589)七月末、その知らせを聞いた真田昌幸は愕然とした、伊達政宗が葦名義広と磐梯山麓摺上原において大合戦に及び、葦名家を滅亡に追い込んだというのだ。これは秀吉の関東奥惣無事令に違背する行為であり、秀吉の怒りの矛先は、北条家ではなく伊達政宗に向くことは明らかだった。
「伊達家が滅んでしまえば、それに驚いた北条家が秀吉に服従を誓うことは必定だ」
そうなれば昌幸が功を挙げる機会はなくなり、真田家は得るものがない。昌幸が、信州の一国衆という地位から雄飛する機会は永遠に失われるのだ。
希代の謀略家・真田昌幸の脳細胞が動き始めた。
『椿の咲く寺』
武田家滅亡後、山中に潜伏した今福丹波守・善十郎父子は、家康暗殺を目指し、久能城下に姿を現した。それというのも、家康が少ない供回りを連れて、久能城下を通過するという情報を掴んだからである。
今福丹波父子は、海寂院の庵主・妙慧尼に暗殺計画を打ち明け、協力を仰ぐ。妙慧尼は丹波の娘にあたり、善十郎の妹であったからである。
妙慧尼は、私怨を晴らすことだけが目的の父子の行為を押しとどめようとするが、父子は聞き入れない。説得をあきらめた妙慧尼は、ある策を父子に提案する。その策とは――。
『江雪左文字』
「刀は鈍いように見せておかねばならぬ。いざという時にだけ、その切れ味を見せればよいのだ」
父の遺言を胸に抱き、江雪は戦国の荒波に乗り出していく。
主家である北条家が滅んだ時、秀吉に命を救われ、その御伽衆となった江雪だったが、伏見城の割り普請で、うっかり石田三成に刀の切れ味を見せてしまったため、恨みを買う。
やがて秀吉が死し、天下は動乱の様相を呈してくる。いち早く家康に通じた江雪は、家康の天下取りのために奔走するが、三成に先手を打たれ、無念の臍を噬む。
その後、下野小山陣で三成の挙兵を聞いた家康は、江雪を上方に潜行させ、小早川秀秋の説得に当たらせようとする。
交渉の末、「家康に与する」という秀秋の言質を取った江雪であったが、秀秋は凡庸な男で、いざとなればどちらにつくかわからない。
関ヶ原合戦が始まり、西軍有利のまま戦況は推移する。この戦況を見た秀秋は西軍に与そうとするが、その時――。
書籍データ
・ 価格 : 税込1,785円
・ 単行本 : 277ページ
・ 出版社 : 光文社
・ ISBN : 978-4-334-92781-3
・ 発売日:2011/10/18
書評
『城を噛ませた男』切れ味鋭い戦国ものの短編
日本経済新聞夕刊2011年11月16日付 文芸評論家 縄田一男
今年、最もエネルギッシュな活躍を見せた伊東潤の最新短篇集である。
しかも収録された5作はいずれも切れ味鋭く、優れた短篇のお手本ともいうべき出来ばえ。
いま、戦国ものの短篇を書かせて最も優れているのはこの伊東潤と岩井三四二の2人にしくはない。
まず、表題作の城を噛(か)ませたの一言が、非常に強い印象を与え、さらに、Make him attack the castle と書かれた英題がまったく違和感なく、作品を力強く後押ししている。
まずは、人間の野心というものを知り尽くした真田昌幸の鬼謀が戦慄のクライマックスを迎える表題作以下、北条と上杉の間で表裏者となることを繰り返し、辛うじて命脈を保ってきた佐野家の命運を二人の物見を通してシニカルに描く「見えすぎた物見」、非情な忍びの一抹の人間味をとらえた「椿(つばき)の咲く寺」、さらにラストの1頁(ページ)が利いている「江雪左文字」等、甲乙つけがたい力作。
その中で私がいちばん好きなのは、味方にさえ馬鹿(ばか)にされてきた鯨取りの親方が、苛酷(かこく)な戦いで落城必至の城を守り抜くさまをユーモアすら交えて描いた「鯨のくる城」だ。
大満足の一巻。
評価★★★★★(5段階評価)







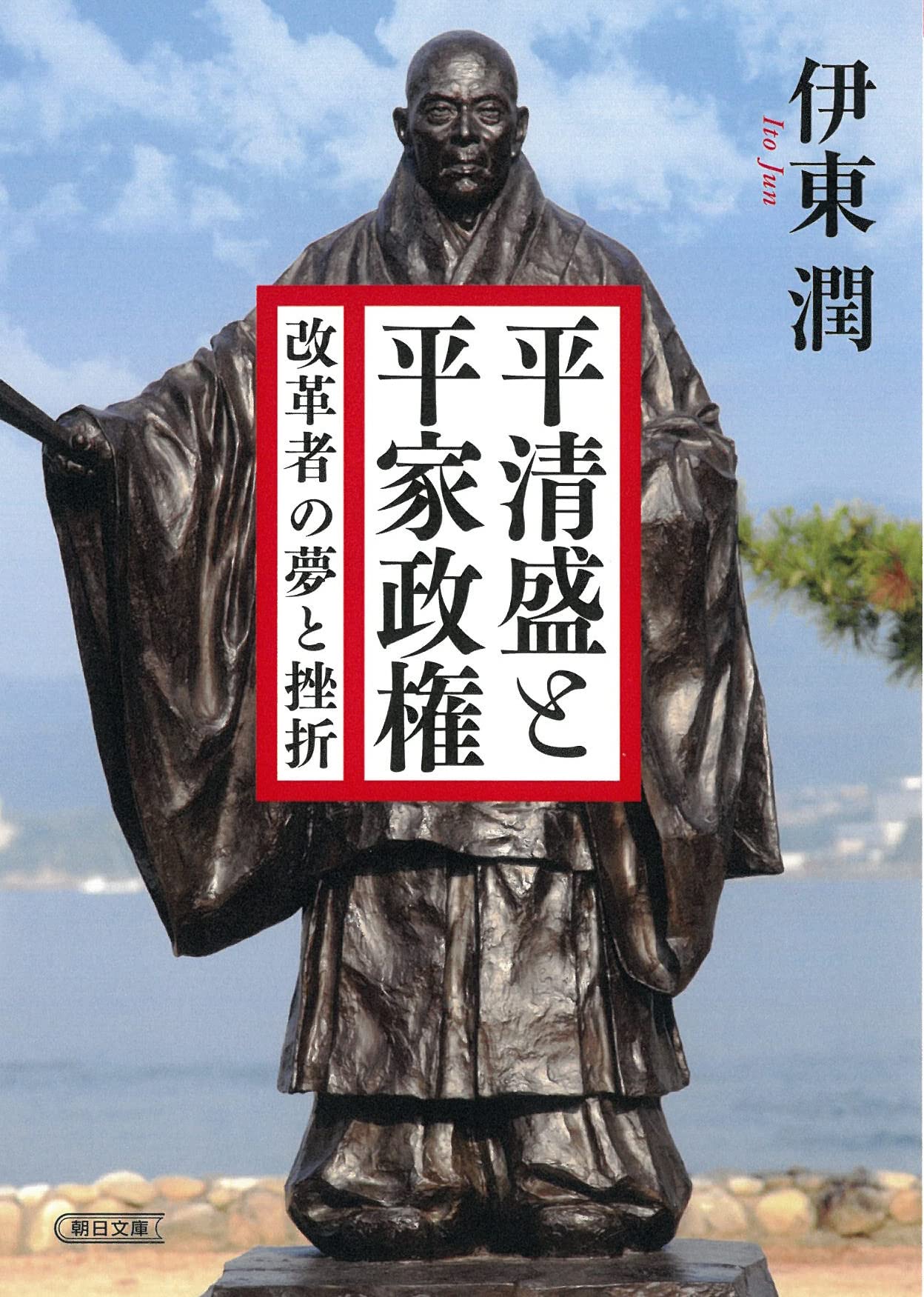









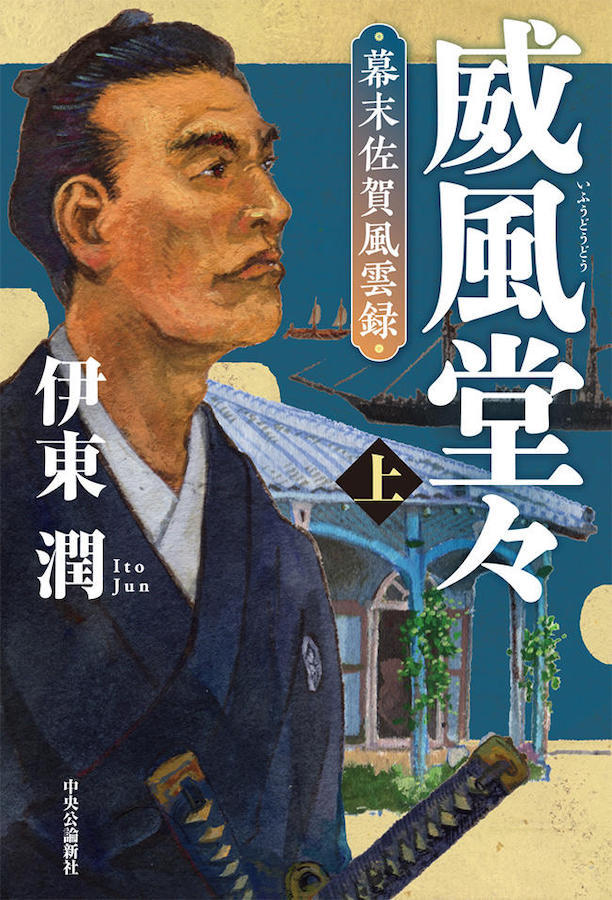




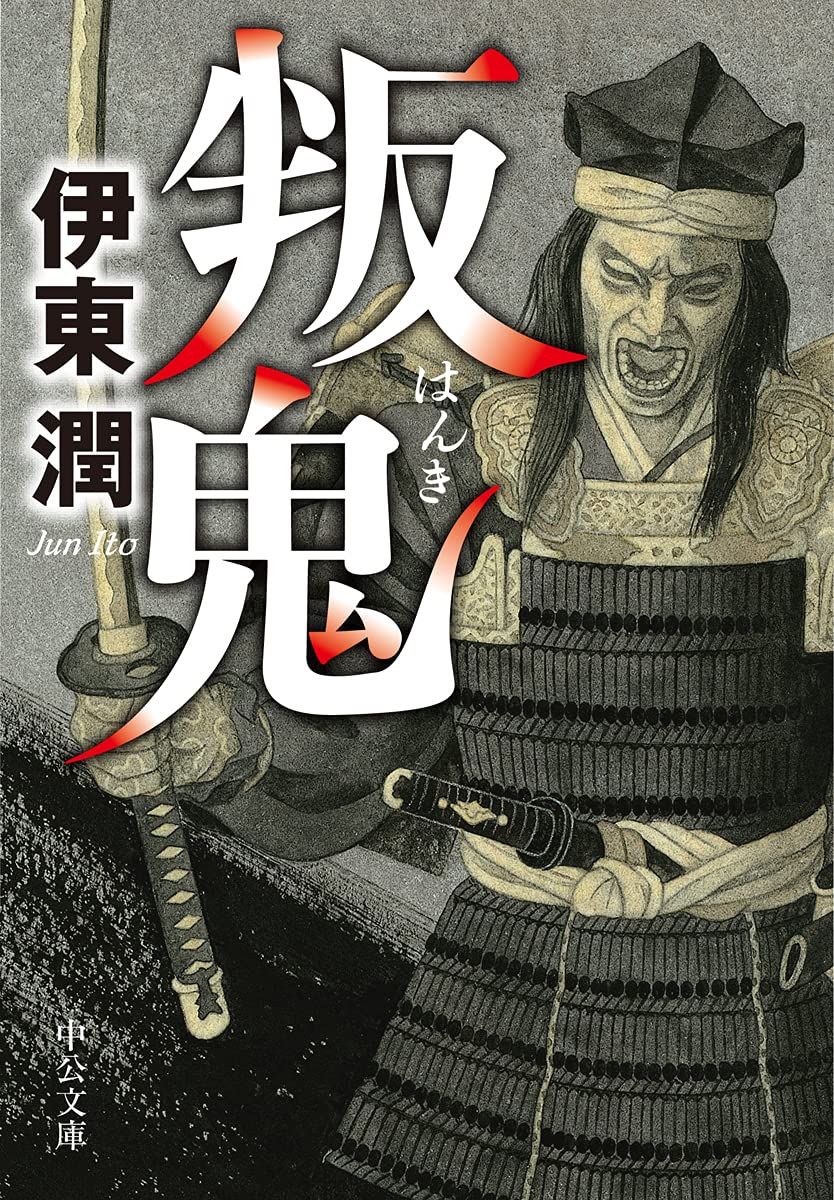
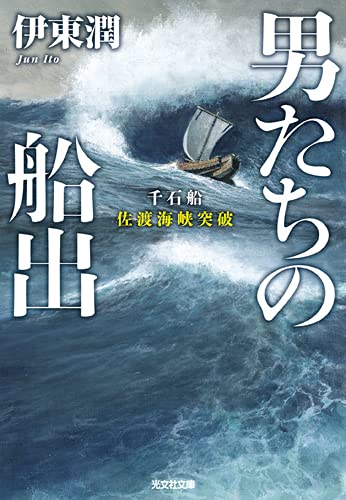













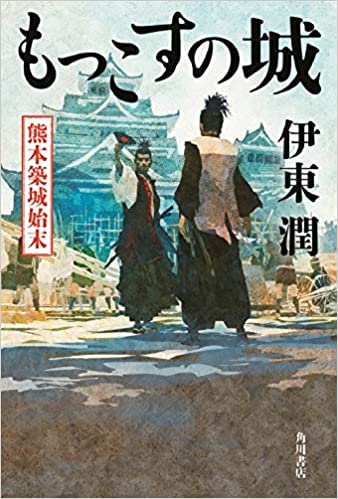





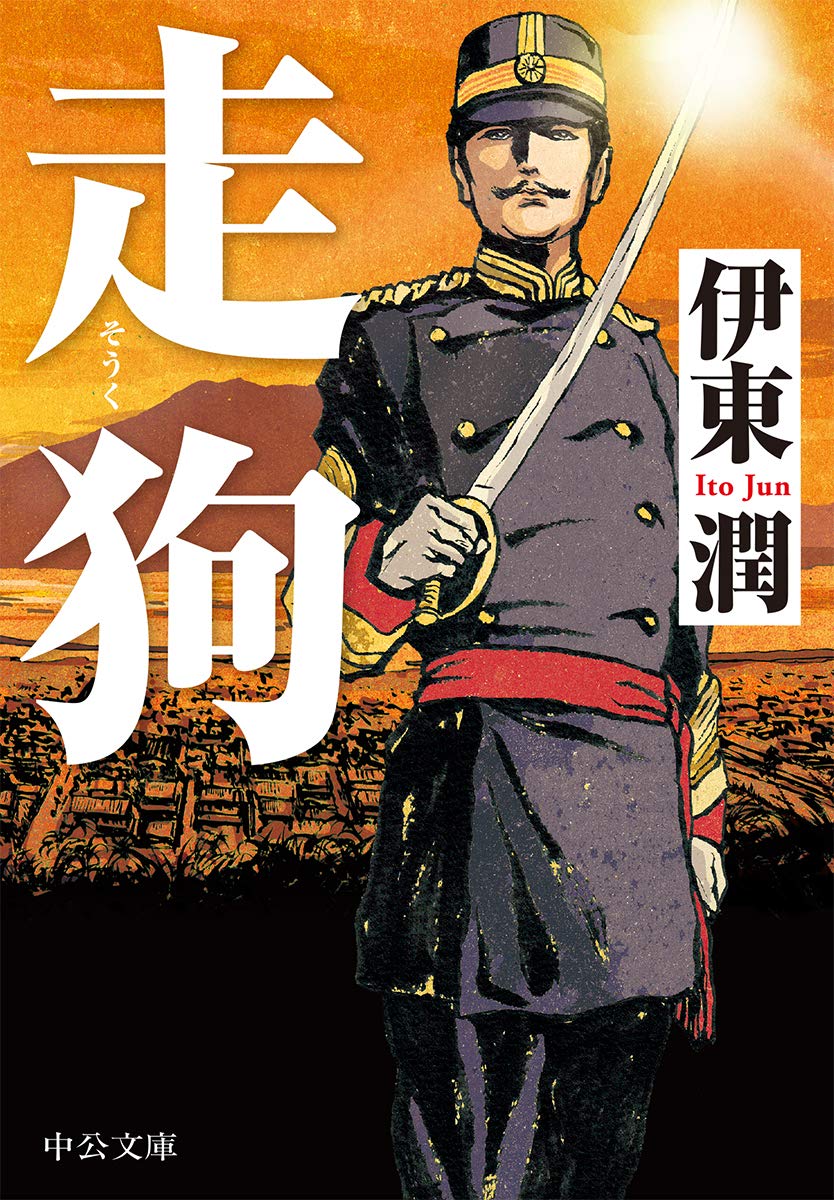



作者より
2010年に「小説宝石」に不定期連載していた短編が、いよいよ単行本となりました。
タイトルは、その中の一篇から取り、『城を噛ませた男』としました。
この短編集は、長年にわたって温めてきた企画を惜しげもなく放出したものです。
短編の構想は、なかなか編み出しにくく、いつも頭を悩ますのですが、長い間、熟成してきたものばかりなので、必ずやご満足いただけると思います。
なお、それぞれの作品には、テーマが設けられています。歴史小説は「面白かった」というだけでない「何か」を提供するのが使命であり、それは「現代社会の写し鏡」であるべきだと思います。
しかし、それぞれの作品に盛り込んだ「何か」については、ここでは語りません。実は語りたくてうずうずしているのですが(笑)、やめておきます。
なぜかと言えば、それを読者各位に考えていただくのも、読書の楽しみであるからです。